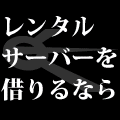2026年1月19日(月) 04:10 JST
ゲストユーザ: 風呂好き
現場監理上での問題なのですが・・・。
よろしくお願いします。
地中梁と土間スラブのコンクリート打設ですが
地中梁天端はGL、1FL(土間スラブ天端)はGL+500となっています。
地中梁天端より1FL(土間スラブ天端)まで地中梁補強筋が構成されています。
現場での施工手順は土間スラブ下端(スラブ厚150)までコンクリート打設を行い
次に土間スラブ配筋を構成して、土間スラブのコンクリート打設となります。
このとき、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成19年版(P403)
に描かれている土間スラブ打ち継ぎ補強(シアコネクター)は
必要なのでしょうか?
また、土間はスラブ配筋(ダブル配筋)の場合シアコネクターはダブルに
なるのでしょうか?
すべて一体でコンクリート打設をしてゆけばシアコネクターなどは不要に
思いますが、現実は不可能ですので、上記のように土間スラブ下端までの
打設となります。
アドバイスお願いします。
構造計算 & 構造図はどうなっているのでしょうか?
一般的に 土間スラブ(土間コン)で 解いていれば 必要ないはずですが
1Fのスラブで 解いていたら 補強は必要だと思います
1Fのそのスラブの荷重を (杭)基礎・地中梁で持たせている ->1Fスラブ
基礎等と関係なく 地盤でもたせてるのであれば -> 土間スラブ(土間コンクリート) だと認識してますが・・・・・
だいおー/大内
だいおー/大内
ゲストユーザ: ビルネ
標準仕様書は、土間スラブと土間コンクリートを明白に
使い分けられていると思います。
・土間スラブ---------スラブ扱い。置きスラブとも言います。
・土間コンクリート---床荷重を直接、地盤へ流します。
標準仕様書の(c)土間スラブの打継ぎ補強の中間部および端部におけるスラブは、両方ともダブル配筋のスラブを想定した図であると思います。この場合、中間部は基礎梁の上に載っかるだけで、固定端となり得ますので、打ち継ぎ補強筋はシングルで構わないです。
その代わりに端部の打ち継ぎ補強筋は、スラブのダブル配筋(破線表記)に沿わせて、ダブルで配筋しているもの考えられます。
しかし、これは、あくまで特記が無い場合の配筋です。もし、構造計算の方で端部固定ではなく、端部支持(ピン)として計算されているのなら、シングルの打ち継ぎ補強筋でも構わないはずです。
また、土間コンであっても、土間コンに剛床を期待する場合には、シアコネクターを入れる場合もあります。
まずは、やはり
構造計算 & 構造図はどうなっているのでしょうか?
この確認が最優先でしょう。
1.配筋標準図、特記を確認する。
2.土間スラブなのか土間コンなのかを見極める。
(構造図の該当スラブにS符号が付いていれば、スラブ扱いの可能性は高いが必ずしもそうとは限らない。
3.それでも不明な場合は設計者へ確認する。
工事監理とは、工事を設計図書と照合し、その通りに実施されているかを確認することです。設計図書に疑義がある場合には、まず、設計者と施工者との協議が必要です。
ゲストユーザ: 風呂好き
daiohさん
アドバイスありがとうございます。
> 構造計算 & 構造図はどうなっているのでしょうか?
ですが、以前、設計者に聞きましたところスラブと答えが返ってきました。
実は今回、設計者と監理者が別発注になっていまして
設計図面に関しての質疑などを起こしているのですが
「監理者の判断」という回答が多いです。
今回の問題も質疑として起こしたいところですが
多分「監理者の判断」という答えになってしまうと想定されます。
仕方なく、答えを模索しているのですが、悩んでしまい
ここの掲示板に書くことにしました。
耐震壁内の電気版周囲の電気配管についてもこの掲示板でお世話になったのですが
基本的には「監理者の判断」ということばで答えが返ってきます。
設計者と監理者が違う場合は難しい点が多いと苦慮しています。
サイド設計者に確認をしてみます。
ありがとうございました。
ゲストユーザ: 風呂好き
ビルネさん
アドバイスありがとうございます。
以前、設計者に土間コンクリートなのか、スラブなのかを確認したところ
スラブと答えが返ってきました。
(今回、設計者と監理者が別発注です)
施工業者としてはスラブ下端まで地中梁のコンクリートを打設し
その後、土間スラブの打設という方法で施工するようです。
今回、地中梁天端より土間スラブ天端までが500㎜ほど落差があり
その落差を地中梁天端補強筋として配筋が表現されてします。
今回の打設方法ですが、この補強筋の途中で水平打ち継ぎが出てしまう
形になります。そこで、今回のようなケースは乗せ掛けスラブなのか??
と悩んでいました。特に構造図にはそのような場合の指示はされていませんでした。
いろいろアドバイスありがとうございます。
参考になりました。
再度、設計者に確認してみます。
・・・設計者から「監理者判断」と回答が返ってくるのが一番辛いのですが
質疑を数点行っていますが「監理者判断」という答えが多いです。
答えを出してくれると良いのですが・・・(-_-;)
ありがとうございました
ゲストユーザ: 風呂好き
daiohさんへ
すみません、ログインしないで「ゲスト」でコメントを書いて
しまいました。最初の質疑者の「風呂好き」と「ゲスト」の「風呂好き」は
同一人物です。
ゲストユーザ: ビルネ
(今回、設計者と監理者が別発注です)
・・・・・
設計者から「監理者判断」と回答が返ってくるのが一番辛いのですが
質疑を数点行っていますが「監理者判断」という答えが多いです。
色々と事情があるでしょうから、あえて、そこは触れずにおきます。
素っ気無い回答しか得られないのであれば、質疑方法を工夫するしかないでしょう。例えば、回答案、解決案を提示し、「これで宜しいでしょうか」と確認を取る形式とか。
いずれにせよ、監理業務として請けられている以上、何か問題があった時には、何らかの責任問題が発生してきます。面倒でも、きちんと手順をふみ、監理業務の内容を逐一記録しておかれた方が良いでしょう。
また、転ばぬ先の杖として、『イラストで読む! 建築トラブル法律百科 最新版』や、ピックアップ関連書籍等を一読されておかれることをお薦めします。
ゲストユーザ: 風呂好き
ビルネさん
参考の本までご紹介ありがとうございました。
設計と監理が別発注の難しさを痛感しています。
結局、まともな回答は得られそうにありませんでした。
私どもの協力構造設計事務所などの相談しました結果
アドバイスとしてしか扱えませんが、・・・
地中梁補強筋天端はスラブ天端まで到達していて
その補強筋部分にスラブの鉄筋が通し筋として配筋される場合
2階の梁とスラブとの関係と同じ。
2階の梁とスラブであれば基本的には梁とスラブは同時に打設できるので
問題ない。今回は地中梁ということで、スラブ下端で一度打ち継ぎができる。
これをシアーコネクターなどのような方法で補強筋を入れ込みと
鉄筋が混み合いコンクリートのまわりが悪くなる。
土間のスラブといっしょに地中梁も打設しようとすると地中梁の
型枠をすべて殺ししまう。
施工上やむをえないとして、土間下端で地中梁補強を打ち継ぐ。
土間下の土は十分に天圧かけておく。
スラブの端部の部分は地中梁に定着させる。
定着長さは地中梁補強部分はカウントしないで、本来の地中梁部分のところで
定着させる。
こんな具合に落ち着きそうです。
ゲストユーザ: ビルネ
地中梁補強筋天端はスラブ天端まで到達していて
その補強筋部分にスラブの鉄筋が通し筋として配筋される場合
2階の梁とスラブとの関係と同じ。
あーそうか、打増し補強筋が元々あったわけですね。少し勘違いしていました。
それなら、別途に打ち継ぎ補強筋は必要ないでしょう。
ちなみに、もし、せん断がきつい場合で、かつ、打ち継ぎが発生する場合、確かに別途に打ち継ぎ補強筋を追加したりするとコンクリートの回りに影響します。こういう時は、あばら筋及び打増し補強筋のピッチを細かくし、打ち継ぎ補強筋を兼用させるのが一般的でしょう。
風呂好きさんの最終案と同じ方法を私も何度か採用したことがあります。その時の経験から注意点を記しておきます。
おそらく、打増し補強筋(コの字型のかぶせ筋及び軸方向筋の両方)は、地中梁のコンクリート打設前に配筋されていると思います。したがって、特に次のような注意が必要です。
1.打設直後に補強筋に付着したノロをきちんと落とす。
2.型枠解体、土の埋め戻し及び転圧にあたり、トラックやミニユンボ等の作業車輌が乗り入れる際に、補強筋が好き勝手に傷められないようにする。
そういう意味で標準仕様書のような置きスラブ方式は、上記2点に対して比較的、楽に対処できるというメリットがあるんでしょう。
いずれにせよ、協力構造設計事務所があるんでしたら、負担が掛からない程度に、できる限り、そこに、まず、相談にのってもらうのが良いですね。 ゲストユーザ: 風呂好き
ビルネさん
いろいろとお世話になりました。
> 1.打設直後に補強筋に付着したノロをきちんと落とす。
> 2.型枠解体、土の埋め戻し及び転圧にあたり、トラックやミニユンボ等の作業車輌が乗り入れる際に、補強筋が好き勝手に傷められないようにする。
アドバイス参考に現場をすすめたいと思います。
ありがとうございました。
時刻はすべて JST , 現在の時刻は 04:10 午前
- 通常
- 注目トピック
- ロック済
- 新着
- 注目トピック 新着
- ロック済トピック 新着
- ゲストユーザの投稿を見る
- 投稿可能
- HTML許可
- バッドワードをチェック