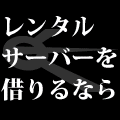2026年1月19日(月) 02:37 JST
ゲストユーザ: 堀越
国道23号(旧国道1号?)木曽川大橋のトラス破断に続き、国道7号本荘大橋(秋田)でもトラス破断。点検の真っ最中に「どかーん」と切れたとのこと。
日経BPより
秋田・本荘大橋で腐食したトラスの斜材が点検中に破断2007/09/06
国交省、東北地方整備局9月1日発表
一般国道7号 本荘大橋全面通行止め実施(第2報) google map
こっちは、木曽川大橋の国交省、中部地方整備局6月25日発表(PDF)
一般国道23号木曽川大橋で道路を支える鋼材が破断(第4報) google map
いずれも、完成から40年程過ぎた鋼トラス橋ですが、トラス材が路盤に埋め込まれている箇所で、雨水等の浸入、路面凍結防止材などの原因で錆びて、破断したようです。他の橋も早く点検しないと、あぶなそう。
ゲストユーザ: 堀越
国交省が「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」を設置するそうです。
また「資格」と「高度専門技術の集積」だそうで・・・。天下り団体までつくるのかな?。(-_-;)
お金と時間の無駄遣いにならないことを祈ってまーーす。
以下、そのまま転載
> 現在、我が国の道路橋は約15万橋を数えていますが、その多くは高度経済成長期に建設されており、今後、高齢化した橋梁の割合が増加することを踏まえれば、これらの構造物を大切な資産として長く大事に保全していくことが重要です。
> 国土交通省では、落橋をはじめとする事故等を未然に防止するため、「早期発見・早期補強」を行う予防保全システムを全国の道路橋へ展開することとし、このために必要な方策をご審議いただくため、橋梁工学や維持管理に関する専門家の皆さんをメンバーとする「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」を設置し、第1回会議を開催します。
>同会議では、
> o 橋梁点検の制度化と点検資格
> o 全国データベースと高度専門技術の集積
> など、道路橋の安全性を確実化するための方策について検討し、その結果は順次、予算や施策に反映していきます。
>1. 第1回会議について
> 開催日時 : 平成19年10月24日(水) 15:00~17:00(頭撮り及び傍聴可能)
> 場 所 : 国土交通省(中央合同庁舎第3号館)11F 特別会議室
>2. 「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」の構成
> 座 長: 田﨑 忠行 日本高速道路保有・債務返済機構 理事
> 池田 道政 土木研究所 理事
> 上田 多門 北海道大学大学院 教授
> 大山 耕二 岐阜県 中津川市長
> 川島 一彦 東京工業大学 教授
> 城處 求行 日本道路交通情報センター 副理事長
> 道家 孝行 東京都 建設局長(兼:建設局 道路監)
> 西川 和廣 国土交通省 国土技術政策総合研究所 研究総務官
> 藤野 陽三 東京大学 教授
> 三木 千壽 東京工業大学 教授
> 宮川 豊章 京都大学 教授 (以上、50音順)
ゲストユーザ: 小水流
天下り団体等の賛否の話もありますが・・やはり公共インフラの敷設時期から見て、対策が急務なのは間違いないです。
日本では1960~1980程度・アメリカでは1950~1970程度が投資のピークのはずなのですが、、
この期間の公共インフラが、実はかなり危険です。分かり易いのは首都高とか。
財政的にある程度見通しの立てられるニューヨークでさえ、当時に張り巡らされた公共インフラが、
老朽化による補修・改修時期に到達しており、都市を維持するという観点から危機が目前に迫っていると、
何年か前に国営放送のドキュメンタリーで見たことがあります。
首都高速がいつか無料という幻想を流布してしまう日本国では言ってはいけないことなのかも知れませんが、
都市インフラは生まれた日から老朽化が始まり継続メンテナンスが必須なので、
公共インフラのメンテナンスを比較的軽視してきた日本のツケは、一般認識よりも悲惨な状況だと思いますよ。
悲しいことに日本は、「必要になったら工事するから効率がよい」という建前で、
現状300mmの埋設管が来年350mm必要・再来年400mm必要・5年後500mm必要という場合、
その都度工事してしまうという無闇な費用投下を都市にしている歪なクニなので、
現状300mmの埋設管を先を見込んで500mm投入するクニ(欧米&金余り産油国)に比べて、
倍以上の費用を無駄にしてきたという負の遺産を持っています。
今回の動きがどちらに転ぶかとは別次元で公共インフラのメンテナンスと非破壊検査による維持管理に、
社会的関心と予算を向けるべきではあるのですが・・向く確立は非常に低いです。
今後公務員になる人がここを見る確立は皆無なので書いても意味が薄いかも知れませんが、
10~20年後に現役の公務員&政治家の皆さんは、用意された危険な遺産の相続について、
覚悟だけはしておいた方がよいと私は考えます。
ゲストユーザ: 堀越
いままで、日本の公共工事は「作れ作れ」の大合唱。税金も当然そっちぱっかに使ってた。当然、維持補修は後回し、予算は無し、で過ごして来た。
既に、そのツケはとっくのとうに出ていた。なのに先送りした結果の一例が、本荘大橋や木曽川大橋・・・。トンネルの剥落も似たようなモン。
改修するときに、前工事の欠陥が判っていても「手は付けない」、「目をつぶる」。何十年もの悪習慣の積み重ねも原因の一つ。
既に完成した構造物の維持保全も大切だが、新規に作ったモノも、完成と同時に維持保全が始まる。
「落札率が高いから業者が儲けすぎている」、「落札率が低いから税金の無駄遣いがない」と言う論議も事の根幹を見ていない。私は「落札率だけで見るのは間違ってる」と断言する。工事費と出来上がったモノの耐久性を同時に評価し判断すべきと考える。この見方をしない限り、どんなに論議をしても、出来上がったモノに費やす無駄な維持修繕費は減らない。
落札率ばかり注目される今時の公共工事の遺産は、50年経ったら、さてどうなるのか。余計に心配。
建築物だって同じだよー。
ゲストユーザ: 堀越
1.読売オンラインから
国交省調査、道路橋8万8000か所、過去5年点検なし2007年10月24日 22時26分(読売新聞)
遅れている原因は予算と人員が不足するためらしいが、先送りの結果がこれです。
これ、国交省の公式発表はいつかなー。
2.国交省の報道発表
米国橋梁崩壊事故に関する技術調査団の調査結果国交省道路局国道・防災課2007年10月23日
原因はNTSB待ちだって
1.国交省の報道発表
「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」を設置(再録)国交省道路局国道・防災課2007年10月23日
1.2.3.の順に資料を読み進めば「維持保全体制が欠落していたから体制を確立することにした」と話の筋が判るのだが、国交省の発表順は、3.2.1.だ。(1をいつ発表するかは不明)
前向きに事を進めているようには思えない。でも、ようやっと国が動き出したことは確か。
ところで、体制が出来上がって、始動するのはいつになるのかなー。気の長い話では困る。
昭ちゃん/堀越
時刻はすべて JST , 現在の時刻は 02:37 午前
- 通常
- 注目トピック
- ロック済
- 新着
- 注目トピック 新着
- ロック済トピック 新着
- ゲストユーザの投稿を見る
- 投稿可能
- HTML許可
- バッドワードをチェック