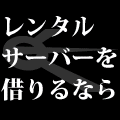2025年10月19日(日) 10:16 JST
ゲストユーザ: 堀越
11/14予定?の施行規則改善(改正とは言いたくない!)により、大臣認定書の写し提出が必要なのは、審査機関が認定書の内容をを確認できる書類を持っていない場合だけとなるようです。
ということは、弱小審査機関で資料を集めきっていない、あるいは運悪く審査機関が当該認定書写しを持っていないときには、従来どおり認定書写しを設計者が確認申請書に添付する必要がありますねー。(-_-;)
施行規則改正後も、認定書(写)のダウンロードサービスを続けるメーカーも多いようです。
日経BP、新潮流フォーカス より
施行規則改正後も大臣認定書のダウンロードサービスを続ける建材・設備メーカー2007/11/12
ゲストユーザ: TKK
>審査機関が認定書の内容をを確認できる書類を持っていない場合だけとなるようです。
どこかの機関を非難する、と言うような意見ではありませんが、
素朴な疑問です。
「大臣認定書の写し」というものは、設計者でも誰でも手に入りますよね。
ちょっとした「手間と努力」で、各審査機関が、あらゆる認定書の写しを手に入れれば、添付不要でしょ?
なんで、手に入れようとしないんでしょうか?(本当に素朴な疑問でしょ?)
それよりも、大臣が認定したんだから、認定番号を書いておけば、それですむような仕組みがいいなあ。
ゲストユーザ: FAT26
確認審査で、それが求められる性能を満たすものなのか、を細かく見る必要があるのか疑問です。
性能がある、ということで「大臣認定」なんだから、番号があるだけで良いはず。
もし使用条件があるのなら、それを書いておけば済むこと。
肝心なのは、ほんとうにそれが現場で使われてるか、条件通りになっているかどうかの検査かと思いますけどね。
性能がある、ということで「大臣認定」なんだから、番号があるだけで良いはず。
もし使用条件があるのなら、それを書いておけば済むこと。
肝心なのは、ほんとうにそれが現場で使われてるか、条件通りになっているかどうかの検査かと思いますけどね。
ゲストユーザ: まったくその通りだと思います
上でゲストユーザーさんが書かれている通り、いくら書類審査で厳格にしたところで実際の現場がそれを守らなかったら元も子もありません。
基準法改正で、審査の厳格化(?)ばかり取り上げられていますが、実際の検査はどうなっているのでしょうか?
市川で起きた鉄筋不足にしても、性能評価の検査がなかったらそのまま見過ごされていたところです。
ゲストユーザ: 堀越
わーーー。一日留守してたらたくさん書き込みが・・・。(^o^)
TKKさん
ちょっとした「手間と努力」で、各審査機関が、あらゆる認定書の写しを手に入れれば、添付不要でしょ?
行政情報センター(ICBA)が、かき集めてライブラリ作って、審査機関に公開すれば良いんですよ。認定書は公文書だから、認定取得者以外が公開しても著作権法違反にはならないと思う。
TKKさん
これで済む話なんです。さらに、竣工建物の責任は監理者に押しつけられているのだから。
大臣が認定したんだから、認定番号を書いておけば、それですむような仕組みがいい
FAT26さん番号があるだけで良いはず。もし使用条件があるのなら、それを書いておけ
FAT26さん
前にも書きましたが、今回の法改正は「建物を創るための設計図書ではなく、審査をするための設計図書を作れ」という、今までの建築基準法から180度の大転換するという、もの作りに背を向けた見当違いの法改悪をしたから、何から何まで、まさにひっくり返って大混乱になっているのです(進行形)。
簡単な話、皆さんが言われるとおり、監理を「建築主に対して責任を持ち、技術者の良心に基づき、手抜きせず、正しく、真面目」に行うことを示す法律に改正すれば良かったのです。これって、取り立てて難しいことでも何でもないんですから・・・。 心なのは、ほんとうにそれが現場で使われてるか、条件通りになっているかどうかの検査
まったくその通りさん書類審査で厳格にしたところで実際の現場がそれを守らなかったら元も子もありません
ゲストユーザ: 堀越
14日の施行規則(省令)改正で、大臣認定書の添付を義務づけた「第一条の三第一項第一号ロ(3)」は次のように変わった。
(3)次の表四の各項の欄に掲げる建築物当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
一見、もう認定書(写)を添付しなくて良い認識に陥いるが、検査機関が認定書(写)を集めきるまでは、無条件に添付する義務が生じるのだ!。まして、検査機関の勝手で拡張解釈可能な「その他の理由」まで入っている。
認定書は国交省自身が発行しているのだから、国交省自らが、検査機関に無条件に認定書(写)を提供すべき義務が有ると考えるのが正しい。でも、たぶんめんどくさいから、そんなことはしないだろう。
結果として、おそらく当分の間、検査機関は、自ら認定書(写)集めるより簡単で手間の掛からない方法として「申請者が添付したものを部内用にコピーする」ことで収集すると言う、ずるい考えを実行しようとするだろう。個人的には、そんなだらしない検査機関が出ないことを期待したいが、玉石混交の現状では、この期待は裏切られると思っている。
もし、こんなことをする検査機関に出会い、その行為に納得せず、自ら防衛策を講じるには、添付する認定書(写)のコピーを、再コピー不可能な用紙(コピーすると真っ白か真っ黒にしかコピーできない)にコピーすれば良い。例えばこんなものがある。
最後は話題の本筋から離れてしまったが、改めてここで確認検査機関・適判機関のまともじゃない指摘内容を書くまでもなく、一部に信頼できない確認検査機関・適判機関(員)がいるから、こんな話が出てくる。
ゲストユーザ: 堀越
時事ドットコムから2007/12/06-12:24 住宅着工減で追加対策=支援センター設置など4項目-国交省
建築確認申請の方法などについて面談形式で相談に応じるための「建築確認申請支援センター」を各都道府県に設置することが柱。7日発表。
建築行政情報センター電話相談窓口がパンクしていると言うことですな。でも、県庁所在地だけに作られても、面談方式だとわざわざ出かける手間と時間が・・・。まさか要予約??。 ゲストユーザ: 堀越
改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について平成19年12月7日、住宅局建築指導課
全文転載します。
国土交通省においては、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、各般の対策を講じているところですが、建築確認に関する現状等を踏まえ、さらに以下の取り組みを行います。
1. 建築確認申請支援センターの設置 ~中小事業者への技術的支援~
具体的な物件を手がけている中小建設業者、大工・工務店等のなかで建築確認申請に困難をきたしている状況があることを踏まえ、(社)日本建築構造技術者協会(JSCA)や各都道府県の建築士事務所協会の会員等が、構造基準の見直しへの対応、新しい申請図書の作成方法等を面談方式等で直接アドバイスするサポートセンターを設置する。(相談は無料で受付)
(1)中小建設業者による鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建築物
: 各都道府県1カ所を原則に全国的に設置
((社)日本建築構造技術者協会(JSCA))
(2)大工・中小工務店による木造3階建て・混構造の住宅
: 木造3階建ての建設件数の多い10都道府県に設置(建築士事務所協会)
(その他の地域は、(財)日本住宅・木材技術センターで一元的に対応)
2. 建築確認円滑化対策連絡協議会の設置
~審査側・設計側の意志疎通の円滑化~
各都道府県ごとに特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関及び建築設計団体(建築士事務所協会等)からなる協議会を設置し、審査側・設計側の意思疎通の徹底を図ることを通じ、建築確認手続きの円滑化を促進する。
3. 計画変更の円滑化のためのガイドラインの策定
計画変更手続きを要しない軽微な変更や当初の申請においてあらかじめ幅のある計画内容について確認を受けておくことにより計画変更手続きを不要とする方法について、参考事例や手順等を示すガイドラインを作成。
※テナントビルや先端工場における計画変更、マンションにおけるフリープランへの対応
4. 構造計算適合性判定機関の業務の効率化等
比較的小規模な物件や単純な構造形式の物件についての審査の合理化(判定の実績等を踏まえたうえで、現在、原則として二人の判定員で実施している判定業務を一人の判定員で行う等)、補助員の活用方策等を示し、構造計算適合性判定機関の業務を効率化する。
また、構造計算適合性判定機関における事前相談の実施の徹底を図る。
構造計算適合性判定員の講習会の追加実施を行う。
5. 間違い事例集の作成
確認審査・適合性判定の実態を踏まえ、典型的な間違いの事例等を示すことで、設計者による適正な図書作成を支援するとともに、審査の迅速化を図る。
6. 都道府県ごとの情報の周知徹底について
建築確認の円滑化に係る各般の対策、中小企業の資金繰り対策(セーフティネット貸付、保証)について、情報の周知徹底を図るため、経済産業省及び林野庁の協力を得て、関係業界に対する説明会を全都道府県において速やかに実施する。
ゲストユーザ: 老鍵屋
もう遅いです
既に倒産する地方中堅ゼネコンも出てきてるし、年末に向けて数社、年度末には数倍以上が倒産
構造設計が数こなせないから、設計が出来ないと言う現実を、一般の人は全くご存じない。
田作の構造屋を虐めたら、日本の景気が左前になるとは、国交省も解らなかったのでしょうなぁ~
構造設計者自身は、今更どうでも良い事、設計料は上げ放題だから。
寝ずに働いたって、従来の半分もこなせないのだから、相談したって前年比50%割れは必至。
私の所へも、悲鳴を上げて設計依頼来てますが、これ以上はやりたくても出来ません(マンパワー)
止めた人はいるし、年金貰えるまで耐震診断しかやらない!と言い切る人も多数。
いよいよ、来るぞ、空前絶後の大不況
国交省冬柴不況と言う名で、歴史に残る事でしょう。
ゲストユーザ: 堀越
既に倒産する地方中堅ゼネコンも出てきてるし、年末に向けて数社、年度末には数倍以上が倒産、構造設計が数こなせないから、設計が出来ないと言う現実を、
「今時の建物から構造設計取ったら何も残らない、いや建物が立たない、不況になる。」に国交省は気がつかなかったんですな。大バカものです。
構造設計者自身は、今更どうでも良い事、設計料は上げ放題だから。
焦っている新規のお客さんだと5割増でもOK。!(^^)!
寝ずに働いたって、従来の半分もこなせないのだから、相談したって前年比50%割れは必至。
(1×150%)×50%=75%。結局設計料は減っている。(/_;)
年金貰えるまで耐震診断しかやらない!と言い切る人も多数。
これが一番良いかも!。でも、今の耐震の入札って極端な低価格入札がまかり通っているから、それ相当の覚悟が必要だが、公共物件なら取りっぱぐれなし、支払期日も厳守してくれる。v(^_^)v
最近は、テーブルの反対側に座っている委員が数十年来の顔見知り、なんてーのが増えてきた。これはこれでまた難問「あなたならまだ力余ってるでしょ」なーんて言われて、善意の宿題etc・・・。でも楽しい。
いよいよ、来るぞ、空前絶後の大不況
国交省冬柴不況と言う名で、歴史に残る事でしょう。
暑い『夏』に、『冬』柴がいじった法律で、季節の『冬』が来る前に建築業界一斉に『冬』に向かって一直線。ウソでもいいから「暖冬」にならないかなー。確かに、記録に残るではなく、前代未聞の国交省が作り出した『歴史に残る』大失態です。まあ、過去には政府・日銀etcの失策が作り出した不況を探せばキリがありませんがね。
えー、この掲示板が歴史に残るように来年も頑張りマース。怖いモンなんてなーいモン。
時刻はすべて JST , 現在の時刻は 10:16 午前
- 通常
- 注目トピック
- ロック済
- 新着
- 注目トピック 新着
- ロック済トピック 新着
- ゲストユーザの投稿を見る
- 投稿可能
- HTML許可
- バッドワードをチェック