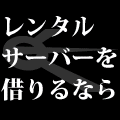2026年1月19日(月) 02:35 JST
ゲストユーザ: 堀越
今法改正で、保有水平耐力計算時の柱・梁・耐震壁の種別(ランク)の決定方法まで告示化(596号)されました。これ、1981年新耐震当時は建設省建築指導課長「通達」でした。
柱とそれに接合する梁の種別が異なるとき、通達では「いずれか最下位のもの。但し、崩壊型が明確なら、塑性ヒンジを生じる部材のうち最下位のもの」との注意書きでした。
これが告示化で通達当時の注意書きがなくなり、「崩壊型に達する場合に、塑性ヒンジが生じている部材の種別に応じて」、「(1)FC・FDが無ければFB、(2)FDが無くFCがあればFC、(3)FDがあればFD」と言う書き方になりました。
判りやすくなったんですかねー、それとも判りにくくなったのか・・・。
ゲストユーザ: 堀越
14日、友人が日本ERI に解釈について問い合わせたところ、「従来(通達の文)と同じで良い」との回答をもらいました。でも、回答が帰ってくるまで半日かかったとか。
ゲストユーザ: zap
Quote by: %E5%A0%80%E8%B6%8A
従来と同じと言うことは、梁ヒンジで梁がFAであれば、柱種別はFAにしても良いということですか?
法文をみると、柱・梁の種別が異なる場合は、最高でもFBにしかならないと読めるのですが・・・ 14日、友人が日本ERI に解釈について問い合わせたところ、「従来(通達の文)と同じで良い」との回答をもらいました。でも、回答が帰ってくるまで半日かかったとか。
ゲストユーザ: 堀越
法文をみると、柱・梁の種別が異なる場合は、最高でもFBにしかならないと読めるのですが・・・
そうなんですよね。特に柱の場合はHo/Dだけでも、FA(Ho/D≧2.5)・FB(Ho/D≧2.0)・FC(Ho/D<2.0)とランクが異なるので、靭性確保の考え方とも関係するので、問い合わせた次第なんです。
法文どおりなら、極端な話、柱個材をFAにする必要は無くなるわけで、靱性の高い長柱にする意味が無くなります。柱FAヒンジ発生、梁FBヒンジ無しの場合でも、柱をFBで評価しなければならないので、???となってしまった訳です。
僅差でランクの低い側の部材にヒンジが発生しなかった場合を考えると、法文は「必ず安全側に評価させる」という意味になります。単なる数値解析である増分解析の不確実性を考慮すれば仕方がないと言う見方も出来ます。
いずれにしろ、講習会が後回しという前代未聞の状態なので、建築センターに質問出して回答もらうしかないですね。
「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」に関する質問受付場所
ちなみに、鉄骨造の種別決めも同じ定義になっています。
ゲストユーザ: 堀越
国交省MLITホー ム > 住宅・建築 > 建築行 政 > 改正建築基準法令(平成18年度改正)
関係告示の項で『※官報上で一部誤りがござい ましたので、訂正させていただきました。【確定版】(8月6日)』だって。下線部が増えている。
告示文引用
>柱及びはりの種別を、次の表に従い、柱及びはりの区分に応じて定めること。ただし、崩壊形に達する場合に塑性ヒンジを生じないことが明らかな柱の種別は、表によらずはりの種別によることとし、種別の異なる柱及びはりが接合されている場合における柱の種別(崩壊形に達する場合に塑性ヒンジを生じないことが明らかな柱の種別を含む。)は、当該柱及びはりの接合部において接合される部材(崩壊形に達する場合に塑性ヒンジが生じる部材に限る。)の種別に応じ、次に定めるところによること。
>(1)FC及びFDの種別が存在しない場合にあってはFBとする。
>(2)FDの種別が存在せず、FCの種別が存在する場合にあってはFCとする。
>(3)FDの種別が存在する場合にあってはFDとする。
「明らかな」の解釈を巡ってまだ一悶着ありそうだ。
私の技術基準解説書は当然「第1版第1刷」で間違ったまま印刷。正誤表と格闘する日が続くのですかねー。「第1版第2刷」を持っている人の記述はどうですか。
時刻はすべて JST , 現在の時刻は 02:35 午前
- 通常
- 注目トピック
- ロック済
- 新着
- 注目トピック 新着
- ロック済トピック 新着
- ゲストユーザの投稿を見る
- 投稿可能
- HTML許可
- バッドワードをチェック